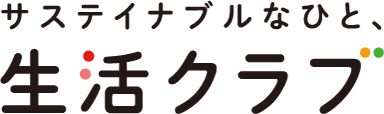遺伝子組換え生物の拡散防止措置緩和に反対するパブリックコメントを提出しました
経済産業省は、「遺伝子組換え生物等の第二種使用等のうち産業上の使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令別表第一号の規定に基づき経済産業大臣が定めるGILSP遺伝子組換え微生物(平成十六年経済産業省告示第十三号)」の一部を改正する告示案を9月22日に発表し、パブリックコメントを募集しました。
≫詳細はこちら(e-GOV パブリックコメント)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595125103&Mode=0
生活クラブ生活協同組合では、疑わしいものを使用しないという予防原則の考えから、1997年1月に「遺伝子組み換え作物・食品は取り扱わないことを基本とする」「やむを得ず使用する場合は、情報を公開して取り組む」と決定し、生産者と取組みを進めてきました。
遺伝子組み換え微生物を環境中に拡散させてしまった場合、完全に取り除くことは不可能です。企業による開発を優先するのではなく、予防原則による安全性の重視を求め、多摩南生活クラブ生活協同組合として、下記のパブリックコメントを提出しました。
該当箇所:第一条の改正と別表を削除することについて
意見:
本改正案は、リスクが低いとされる遺伝子組換え微生物をGILSP区分に追加し、産業利用をしやすくすることを目的としています。概要に書かれている目的には、「生物多様性を確保するための法の理念を損なうことなく我が国のバイオものづくり企業等の競争環境を改善する」とあります。企業の競争力を高めるために、拡散防止措置が緩和されることがあってはならないと考えます。
概要では「リスクが低い」と説明されていますが、具体的にどのような根拠で安全と判断しているのかが示されていないため、一般市民として納得しにくいと感じます。「法による規制の開始以来20年以上を経て、区分適合性の判断をLMMの使用者に任せることが可能な状況となっている。実際、確認の申請を受け付けた後に区分変更を求めたことはない」とありますが、過去20年間違いがなかったからと言って、今後も間違いがないとは言えません。
特にGILSPについては、国際的にOECDが「感染性がない」「毒素を作らない」「安全に使われてきた実績がある」といった基準を示していると承知しています。日本の制度もそれにもとづいているのであれば、どのように国際的な基準と整合しているのかを明記していただきたいです。
パブリックコメントは専門家だけでなく幅広い市民から意見を募る制度です。安全性に関する判断の根拠が示されていないと、どうしても「行政が勝手に安全だと決めているのでは」と感じられてしまいます。一般の人でも理解しやすい形で情報を公開していただくことを要望します。
生活クラブ生活協同組合では、疑わしいものを使用しないという予防原則の考えから、1997年1月に「遺伝子組み換え作物・食品は取り扱わないことを基本とする」「やむを得ず使用する場合は、情報を公開して取り組む」と決定し、生産者と取組みを進めてきました。遺伝子組み換え微生物を環境中に拡散させてしまった場合、完全に取り除くことは不可能です。企業による開発を優先するよりも、予防原則による安全性を重視することを求めます。
≫詳細はこちら(e-GOV パブリックコメント)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595125103&Mode=0
生活クラブ生活協同組合では、疑わしいものを使用しないという予防原則の考えから、1997年1月に「遺伝子組み換え作物・食品は取り扱わないことを基本とする」「やむを得ず使用する場合は、情報を公開して取り組む」と決定し、生産者と取組みを進めてきました。
遺伝子組み換え微生物を環境中に拡散させてしまった場合、完全に取り除くことは不可能です。企業による開発を優先するのではなく、予防原則による安全性の重視を求め、多摩南生活クラブ生活協同組合として、下記のパブリックコメントを提出しました。
該当箇所:第一条の改正と別表を削除することについて
意見:
本改正案は、リスクが低いとされる遺伝子組換え微生物をGILSP区分に追加し、産業利用をしやすくすることを目的としています。概要に書かれている目的には、「生物多様性を確保するための法の理念を損なうことなく我が国のバイオものづくり企業等の競争環境を改善する」とあります。企業の競争力を高めるために、拡散防止措置が緩和されることがあってはならないと考えます。
概要では「リスクが低い」と説明されていますが、具体的にどのような根拠で安全と判断しているのかが示されていないため、一般市民として納得しにくいと感じます。「法による規制の開始以来20年以上を経て、区分適合性の判断をLMMの使用者に任せることが可能な状況となっている。実際、確認の申請を受け付けた後に区分変更を求めたことはない」とありますが、過去20年間違いがなかったからと言って、今後も間違いがないとは言えません。
特にGILSPについては、国際的にOECDが「感染性がない」「毒素を作らない」「安全に使われてきた実績がある」といった基準を示していると承知しています。日本の制度もそれにもとづいているのであれば、どのように国際的な基準と整合しているのかを明記していただきたいです。
パブリックコメントは専門家だけでなく幅広い市民から意見を募る制度です。安全性に関する判断の根拠が示されていないと、どうしても「行政が勝手に安全だと決めているのでは」と感じられてしまいます。一般の人でも理解しやすい形で情報を公開していただくことを要望します。
生活クラブ生活協同組合では、疑わしいものを使用しないという予防原則の考えから、1997年1月に「遺伝子組み換え作物・食品は取り扱わないことを基本とする」「やむを得ず使用する場合は、情報を公開して取り組む」と決定し、生産者と取組みを進めてきました。遺伝子組み換え微生物を環境中に拡散させてしまった場合、完全に取り除くことは不可能です。企業による開発を優先するよりも、予防原則による安全性を重視することを求めます。
多摩南生活クラブ生活協同組合 理事長 椿多見子